記事の内容
この記事では、論理力・思考力・発想力を成長させることに役立つ本を紹介したい。
どの本も、私自身読んでみてとても役立ったものだ。確実に私の血肉になっている。この本たちのおかげで人生が変わっている。大げさではない。
そうした本たちへの愛と感謝をこめて、この場で記事として共有したい。誰かの役に立てればと思う。興味がある人はぜひ読んでみてほしい。
それでは、目次をどうぞ。
考えること
そもそも、「考えるということ」を明確に定義することこそ難題だ。
そこで、今回はざっくりと分類してみる。
考えることの中身を、論理と発想という2つの観点に分けてみたい。そこで、その両方を鍛えられるような本を紹介する。
言語や論理について気になる方はぜひこちらの記事へ。
思考・論理・分析―「正しく考え、正しく分かること」の理論と実践
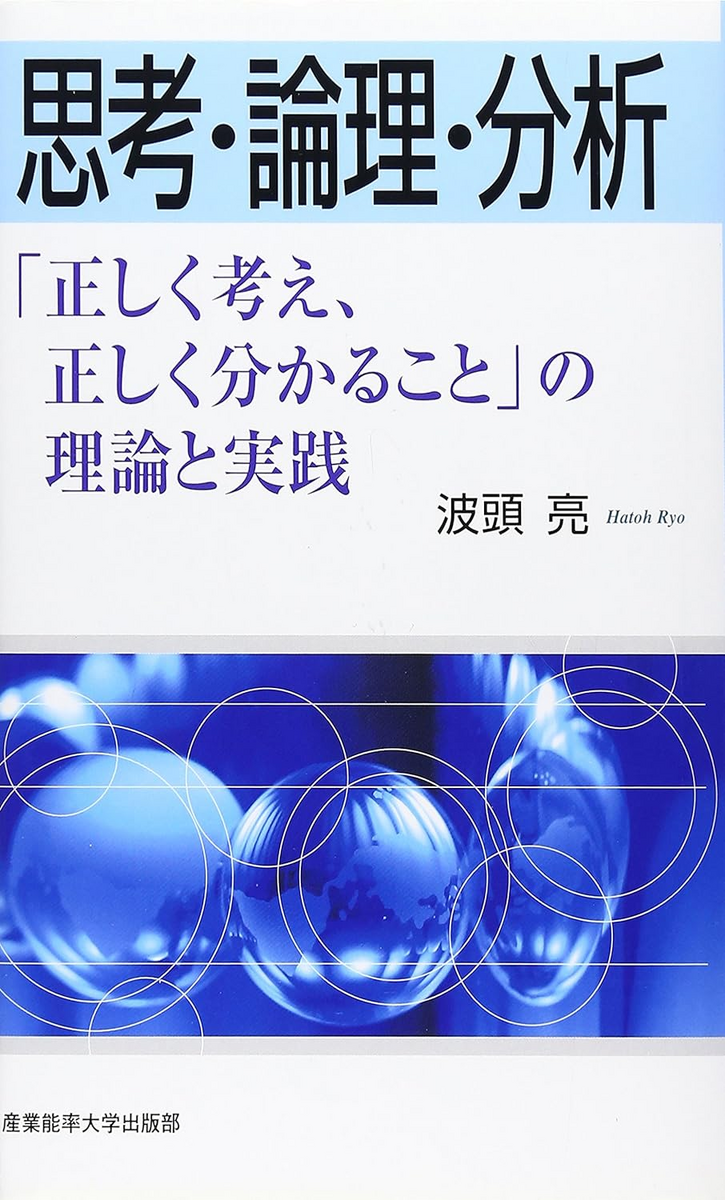
本書は論理的思考という大テーマに真正面から取り組み、「思考」の原論、方法論としての「論理」、そして「分析」のテクニックという三部構成によって、体系的構造的でありながらかつ平易で実践的な解説を行っている。
タイトルの通り、理論がくわしい。
そもそも「思考」とはなんだろう?本書では、すべての出発点となる「思考」の整理から始めてくれる。自分の思考がいかに不明瞭、曖昧だったのかに気が付けるはず。
「分かるとは分けること」
そこで掲示される思考の定義は、とてもわかりやすく納得できるものだ。つづいて、「論理」の説明へとすすむ。こちらも、オーソドックスでわかりやすい。
そして、論理だけではなく、論理の弱点、つまり、人間の思考の弱点についても補ってくれる。認知バイアスに言及がある論理の本というのも珍しいかもしれない。
薄いビジネス書のように、簡単に読める本ではない。しかし、それは読みづらいということではない。自分の思考を確認しながら、じっくりと読んでほしい。
理性の限界、知性の限界 高橋昌一郎
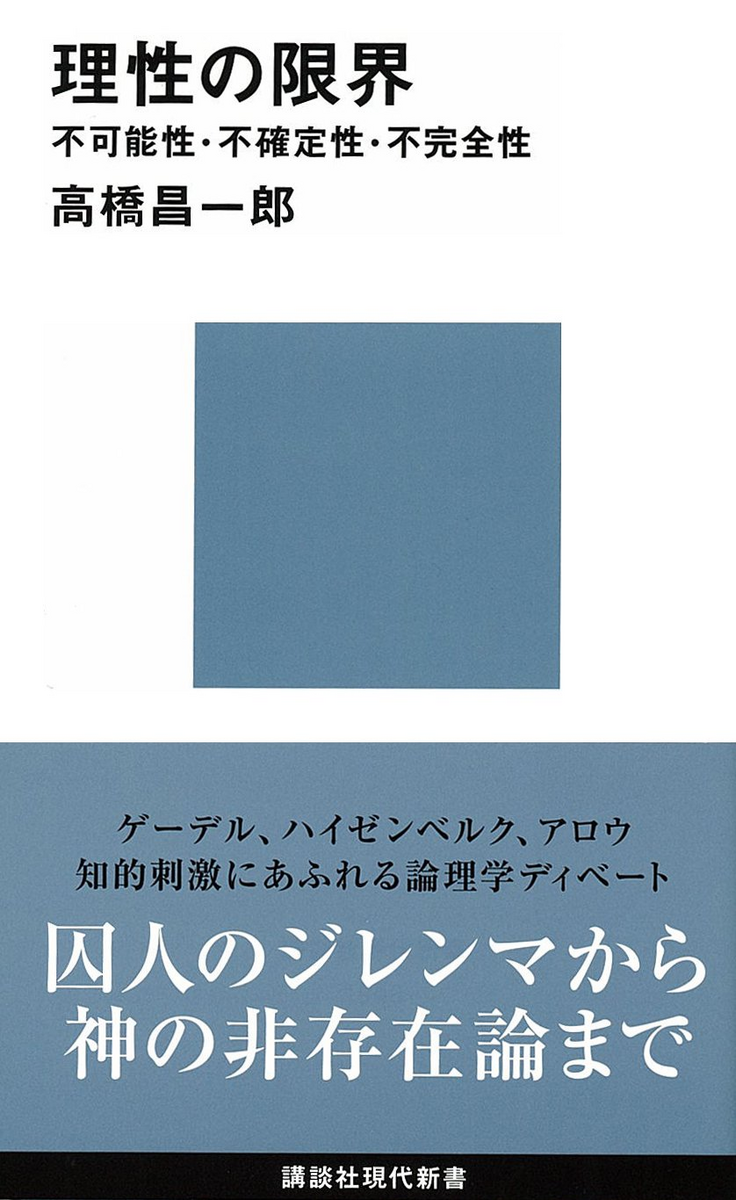
我々が信じる合理的選択、科学的認識、論理的思考は、絶対的なものではない! 世界の根源に関わる事象と密接に関連する人間の「理性の限界」と可能性をディベート形式で平易に描く論理学入門書。
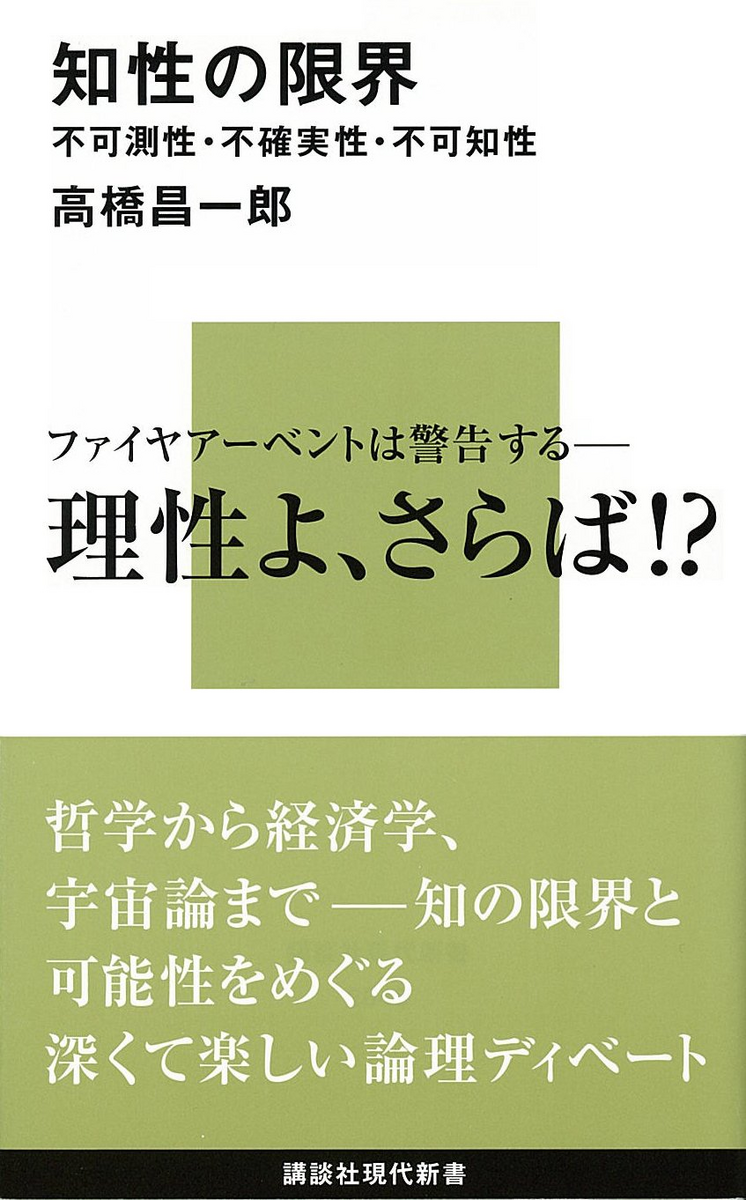
大好評『理性の限界』の著者による熱く楽しい哲学ディベート第2弾。本書では、ウィトゲンシュタインらの論を紹介しつつ、人間の知的営為の基本である「言語」「予測」「思考」の限界と可能性に迫る。
全社会人に読んでほしい本。
人類がたどり着いた知を、楽しい議論で体験できる。高度な論理展開が、会話形式で繰り広げられる。この本の進め方そのものが、論理的に非常にスリリング!!
人類は、考えることによってどこまで知ることができるのか。どこまで考えることができるのか。
抽象的だが、本質的に重要な知恵をもらうことができる本。本書を読むだけで、「知と論理」を楽しむ感覚が分かるだろう。
こうした力を伸ばすには、楽しむことが重要だと思う。だから本書は素晴らしい。
著者が記したこちらの記事も興味深い。
論理トレーニング101題 野矢茂樹

「解説書なんかいくら読んだって論理の力は鍛えられない」と言って論理の実践的な訓練を推奨する著者が、好評だった前著『論理トレーニング』を編み直して、練習問題を101題にまとめたのが本書である。
今回は練習問題のすべてに解答がつけられ、取り組みやすいよう体裁も整えられている。論理を構成する各概念の解説もとっつきやすい表現に直されていて、前作にあった教科書風の素っ気ない印象が薄まっている。
全体は、「議論を読む」と「論証する」に大別されている。前者では接続表現や議論の骨格について、後者では論証構造や演繹・推測、論証の批判について取り上げている。
本書で身につく論理の力にはさまざまな効用がある。たとえば、論証の段で強調している「異論」(相手の主張と対立するような主張を立論すること)と「批判」(相手の立論の論証部に対して反論すること、対立ではない)の使い分け。ここで双方の言葉の概念を正確にとらえ、練習問題によって使い分けが可能になれば、討論のときなどにきわめて有用だ。本書はこうした論理の奥深い世界に読者を案内してくれる。
教科書として作られた本書に、個人で取り組む人が多いというのもうなずける。ひとり本書に向かって言葉と格闘し、煩悶(はんもん)し、その筋道をたどる作業が論理の力を鍛えてくれるはずだからだ。「頭の回転が速い」とか「知性的」というのは、こうした地道なトレーニングの積み重ねに負うところが大きいのだろう。通勤、通学時の1冊としてもおすすめである。(棚上 勉)
Amazon商品紹介より
まさに実践!!
実践しないと、論理力なんて伸びるわけない!!
考えて考えて、じっくりと論理的に考える力を身に着けていくことができる本。
著者は、多数の著作のある哲学者。この本で、論理に慣れたあとは、彼の本格的な哲学書に進んでみるのもいいと思う。楽しく鍛えていける。
考えるということ 知的創造の方法 大澤真幸

何を、いつ、どこで、いかに、なぜ考えるか―。考えることの基本から、書物の力を触媒として活用する実践例、そして、執筆過程の舞台裏まで。刺激的な著作を世に問い続ける知性が、知的創造の現場へと読者をいざなう。
序章 考えることの基本
(1) 何を思考するか
(2) いつ思考するか
(3) どこで思考するか
(4) いかに思考するか
(5) なぜ思考するか
補論 思想の不法侵入者
第1章 読んで考えるということ 社会科学篇
第2章 読んで考えるということ 文学篇
第3章 読んで考えるということ 自然科学篇
終章 そして、書くということ
現代の知の巨人、大澤真幸の頭の中をのぞくことができる一冊。具体的なハウツー本ではない。そんなものでは、彼の思考はとらえられない。
考えることと読むことの楽しさと奥深さを、著者の思索の後をたどりながら体験できる。タイトルに「知的創造」とあるように、考えることによって何かを作り出すということの面白さだ。
具体的な方法論に飽きた人におすすめ。分析だけではなく、創造したい。思考と創造という、これまた楽しい領域へ進みたい方は、ぜひチェックしてほしい。
著者の本との付き合い方にはとても学びが多い。本当の意味での知力を身に着ける一歩へとつながる一冊になるはずだ。
発想
メタ思考トレーニング 発想力が飛躍的にアップする34問 細谷功

メタ思考とは、「物事を一つ上の視点から考える」こと。その重要性はしばしば語られるが、実践するのは容易ではない。そこで本書では、メタ思考を実践するための二つの具体的な思考法(「Why型思考」と「アナロジー思考」)を紹介するとともに、各々のトレーニング問題を多数用意。「タクシー」と「土産物屋」の共通点は?「年賀状がたくさん来る人」はどんな人?…問題を解くうちに思考回路が変わり、考える力が飛躍的にアップする本!
練習問題が豊富なのがいい。
メタ思考という視点で、抽象的に考えるストックを養うことができる。そのために、能力を整理してトレーニングすることができる。
うれしいのが、「アナロジー思考」についての記述が多いところ。
似ているものを見つける。共通する構造を抜き出す。論理だけではなく、アナロジー思考こそが発想へと導いてくれると思う。
ビジネス的な観点での発想の仕方も、多く記載されている。
人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか 森博嗣

熟考したつもりでも、私たちは思い込みや常識など具体的な事柄に囚われている。問題に直面した際、本当に必要なのは「抽象的思考」なのに―。「疑問を閃きに変えるには」「“知る”という危険」「決めつけない賢さ」「自分自身の育て方」等々、累計一千三百万部を超える人気作家が「考えるヒント」を大公開。明日をより楽しく、より自由にする「抽象的思考」を養うには?一生つかえる思考の秘訣が詰まった画期的提言。
Amazon商品紹介より
元工学部教授であり、作家である森博嗣の本。
彼は、本当に思考が鋭く、発想力がとんでもない。そんな彼の思考のエッセンスを感じられる本。
この本の凄さがわかる人は、もうすでに凄い。逆に、この本を読んで、全然大した情報ないなと感じてしまう人は、「抽象性」ということを実感できていない可能性がある。
本書では、具体的な方法論を否定している。なぜか?
発想する、思いつくという現象のロジックは、明快に言葉で説明できないからだ。著者自身も、どうやって発想しているのか本当のところは分からないという。
だから、著者は「抽象的に考えること」の重要性を強調する。
それでは、「抽象性」とはなんだろうか?
抽象的に考えることはどんな利点をもたらしてくれるのか?
それは自分の生き方とどう関係あるのか?
こうした点について、本書はいろいろな角度から述べられている。繰り返し読めば読むほど、色々な発見がある。
問うとはどういうことか 梶谷真司

問いが最も重要である。
問いが全てを開く。
問いそのものを分析する。
知の編集工学

「情報はひとりではいられない」
あらゆる知を編集する編集工学入門。
アイデア大全 読書猿

まえがき 発想法は人間の知的営為の原点
第Ⅰ部 0から1へ
第1章 自分に尋ねる
第2章 偶然を読む
第3章 問題を察知する
第4章 問題を分析する
第5章 仮定を疑う
第Ⅱ部 1から複数へ
第6章 視点を変える
第7章 組み合わせる
第8章 矛盾から考える
第9章 アナロジーで考える
第10章 パラフレーズする
第11章 待ち受ける
アイデア史年表
まとめ
面白そうな本は見つかったでしょうか?
こうした思考そのものを見つめなおす作業もしつつ、本当の知に触れていくのがいいと思う。それがとても面白い。
哲学書や数学書など、学問的な深さのある知の構築物にどんどん進んでいくのがいいと思う。
関連記事
ガイドラインはこちらへ!!!!




