記事の内容
この記事では、ベストセラーになった「言ってはいけない 残酷すぎる真実」という本を紹介します。重要だと思ったテーマをまとめます。

人間の心は進化によってデザインされたと考える進化心理学。つまり、遺伝に関する話がメインの本です。そこで浮かび上がってくる、常識や良識に反するようなデータ、仮説がこの本の面白いところ。たしかに、不愉快に感じる人が多いでしょう。
しかし、われわれ人間はどんな生物なのか、社会はどのように成り立っているのか、冷静に分析するためのヒントになるはずでしょう。気になった方は、ぜひ目次に目を通してみてください。
語ってはいけないタブー?
遺伝の負の側面に注意をはらわなすぎだと、著者は指摘します。親が頭がいいから子供も頭がいい、親が身長が高いから子供も高い。こうした主張はあたりまえにされています。
しかし、
・太った親からは太った子供がうまれる
・子どもが逆上がりできないのは親が運動音痴だからだ
・子どもの性格が暗いのは親が暗いからだ
・子どもの成績が悪いのは親が馬鹿だからだ
このよう負の遺伝もあると考えるのが自然です。しかし、社会規範によりこうした面は封殺されています。しかし実際には、IQの遺伝率は77%もあるという結果があります。
そして、
・精神病は遺伝する
・犯罪は遺伝する
のも事実です。とくに、サイコパスなどの極めて高い反社会性の遺伝率は、81%もあるというのです。
自らの失敗を努力が足りないからだ、と責められ苦しむ人がいます。であれば、遺伝に関する事実によって、心が救われる人も多いのではないでしょうか。
社会的規範により隠されていた事実は不愉快です。しかし、そうした事実を直視する段階に、人類は到達しているのかもしれません。
知識社会での格差
「潜在的な知能は人種にかかわらず均質でなければならない」というのは、イデオロギーである。だからこそ、「人種間に知能の差がある」という科学的なデータは、うけいれられない。
経済格差の根源とは、知能格差であるという。遺伝学の成果を無視した教育制度のままのため、貧困の抜本的な解決が起こりえない。
「知識社会」とは、知能の高い人間が知能の低い人間を搾取する社会のことなのだ。
著者のこの指摘は、もっともだろう。この搾取の構造は、SNSのおかげで可視化されつつある。自分とは立場、環境の違う人間の人生を見ることができるからだ。「格差」が徐々に認識されつつあるように見える。
美貌格差
なぜ私たちは、美男美女が好きなのでしょうか。顔の対称性と肌の滑らかさがあらゆる文化に普遍的な美の基準だといいます。これは、感染症にかかっていないことなどを示したため、進化の歴史において好まれたからだ、と考えられています。
男も女も、美男美女のほうが経済的にも有利です。美女とブスでは経済格差が3600万円もあるというのは有名な研究かもしれません。一方で、容姿がよくない男性の方が、容姿がよくない女性よりも経済的に不利だ、という研究もあります。
美貌格差はいけないことなのでしょうか?美貌が年収に関係してくる社会でいいのでしょうか。
しかし、これは私たち消費者のせいなのです。美男美女の店員からサービスを提供してもらいたい。アナウンサーは美男美女がいい、と私たち市民が思っています。
美貌格差を作り出しているのは、市民一人ひとりである私たちの差別意識のせいなのです。
見た目による差別については、たびたびSNSなどで話題になります。その時、差別を生み出しているのは私たち一人ひとりがもった本能のせいだという事実を忘れてはいけないと思います。
男女平等が女性の幸福度を妨げている?
社会的成功を手にしたはずの女性たちが、家庭に戻っていく現象が観察されます。
彼女らは、自らの意志で仕事から身を引いています。
この背景には、男女では「好きなこと」が違うという事実があります。
性ホルモンの影響により、得意なことが男女の脳では異なる傾向があります。
自然科学分野のなかで、物理学や工学での女性の比率の少なさに対する、生物系の女性比率の多さは、文化のせいではなく生まれつきの好みの違いのせいなのです。
網膜と視神経の構造的な違いから、男女では色の見え方にも差があります。
「男はモノを相手にした仕事を、女は人を相手にした仕事を好みやすい」
これは、文化ではなく、遺伝が生み出したものなのです。
どの先進国でも、女性の方が男性よりも幸福度が高くなっています。しかし、女性の社会進出が進んだ結果、人生の満足度が男性レベルまで下がってしまったという研究もあります。
「幸福の優先順位」が男女では生まれつき違うのではないか、と進化心理学では考えられます。男性は競争に勝つことに満足を感じますが、女性は、家庭と切り離されると人生の満足度が大きく下がってしまうのです。
進化心理学では、「女は女らしい仕事をすればいい」と主張するわけではありません。男女の性差をイデオロギーで否定するのではなく、両者の違いを認めたうえで、男も女も幸福になれるような制度をめざすべきなのです。
事実を徹底的に追及することこそ、よりより社会設計には必要なのではないでしょうか?
うまれつき男と女の心には、違いがあることはたしからしい。人間という生物は、子育てのために男女の役割をわけてきたからだ。進化によって、そのようになっていった。現代の科学によって、男女の生まれつきの違いが見えてくるのは当然のことのように見える。しかし、それを社会という文脈でどう解釈するべきなのかには、慎重であるべきだ。何が良いのか、悪いのか、メリットがあるのかデメリットがあるのか、これらは解釈が分かれる。科学の成果と安易に価値観を結び付けてはいけない。「女性は、社会での競争よりも、子育てに満足度を得やすい。だから、女性は子育てに専念するべきだ。」こう言ってはならないのだ。科学はこう言ってはいない。個人的にも、何が幸福なのかという論点については、とくに慎重であるべきだとおもう。
子育てや教育はこどもへの影響が少ない
別々の家庭で育った一卵性双生児は、なぜ同じ家庭で育ったのと同様に似ているのか?
こどもの性格を決めるのも、遺伝の要因が大きいのです。さらに、子育てはこどもの性格や能力を劇的には変えられません。むしろ、影響が大きいのは友達関係などの非共有環境です。
わたしは、遺伝と非共有環境でわたしになります
わたしたちの脳と心は、旧石器時代のものとほとんど変わりません。つまり、子どもたちも、その時代に合うようにデザインされています。
両親と子どもだけの核家族で育ち、幼稚園に通い、小中高大と勉強し続けるようにはデザインされてはいないのです!!
幼い子どもは親以外の大人を怖がるが、年上の子どもにはすぐに懐きます。
親とのコミュニケーションではなく、同年代や年上の子供たちとコミュニケーションすることが、人類史上ずっと、子供たちにとっては大事でした。だから、親の子育ては、大きな効果を子どもに与えることができません。
こどもにとって、世界とは友達関係のことです
子どもが親の言うことを聞かないのは当たり前です。親ならわかるように、子どもは望んだようには成長してはくれません。
子どもが親に反抗するのは、そうしなければ友達からのけ者にされ死んでしまう環境で、子どもたちは人類史上ずっと生きていたからなのです。
この本はなぜ批判されるのか??
本書を読んだことのある人や、ここまで読んでみて批判したくなった人はぜひ次の記事をよんでみてほしい。
なぜこの本の主張は批判されてしまうのか、考察している。
「遺伝率」という重要な概念に注目する。
より詳しくは、本書へどうぞ。

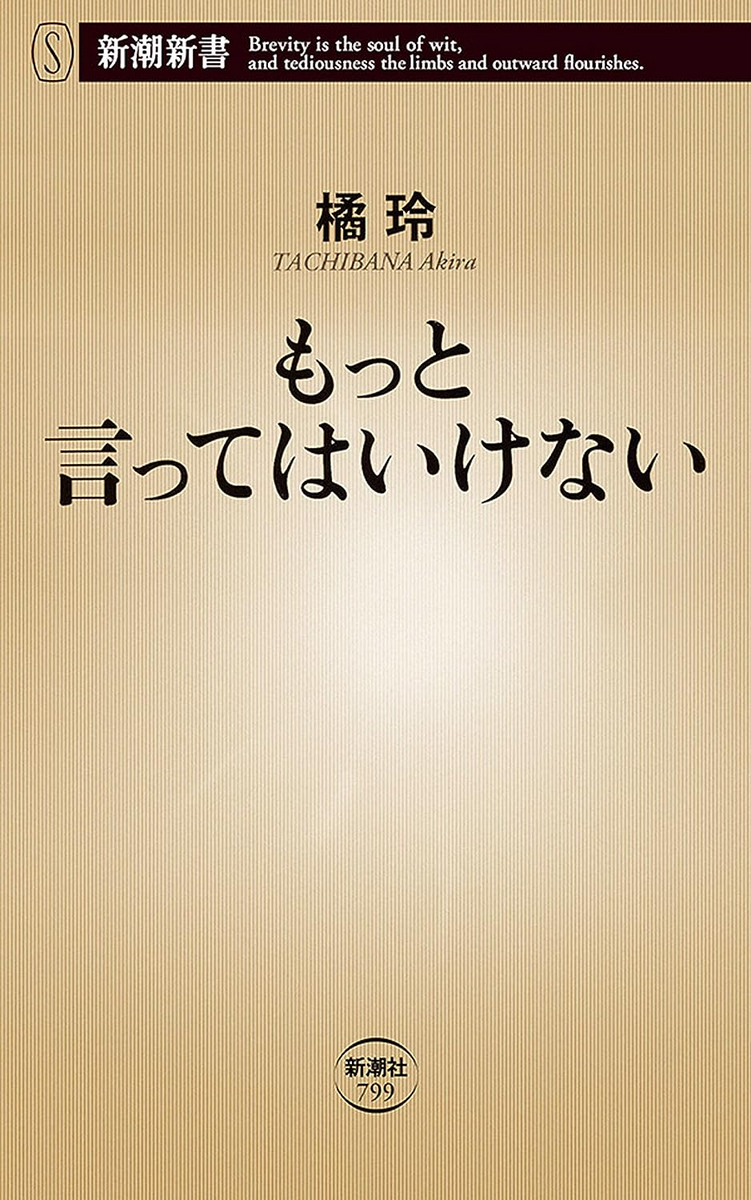
関連記事
進化心理学が気になる方は、こちらへ。




